能登・輪島市輪島崎町(石川県) – この日は輪島のテニス“仲間” 漆芸家・山崖松堂(やまぎし しょうどう)さん(本名 山崖大治)と、お兄さんの山崖宗陽(やまぎしそうよう)さん(本名 山崖大祐)の仕事現場「山崖松花堂」へ。
山崖さん兄弟がつくった深く惚れこむような作品を見させてもらった。

|
『芯漆』のオフィシャル・ホームページはこちら!数十億年先まで残るアートを目指した『芯漆』 |
山崖さんとは年に数回会うか・会わないか…というテニス仲間。会うのはテニスコートの上。
山崖さんは輪島、ぼくは穴水のテニスチームでプレイしているため、練習コートが異なる場所。
普段、もし会うことがあれば、それはテニスコートの上で、ただただ、ひたすらボールを打ち合う仲間である。
1年半前だったか、山崖さんから、「漆器づくりと、販売を仕事にしている」と聞いたことがあった。
その話しからの印象は「あぁ、“塗師屋”さんかぁ!」で、輪島にいる“ふつ~の”塗師屋さんかと思っていた。
が、それは、ぼくの“大きな勘違い”だった。
「まさか!こんな作品が、“ただ~の”テニス仲間からでてくるとは!」と驚いた。
100%日本の漆(うるし)のみでつくられた椀。
「漆のみ」で、基盤となる木の材「木地」を使っていない。
この色の“深さ”と、きめ細かさに見惚れてしまう。
ものにはよるが、製作期間は驚きの約10年前後。15年かかっているものある。全てもちろん手作業。漆を手で塗ることも多々。
「これをつくれる人は数少ない…いや…いない」「これは神業ですよ」と自信に満ちている。
目指すは「国宝」レベルだ。
琥珀(こはく)に近い“質”の“漆”。従来の漆器とは違い、1万年以上はもつ。もはや半永久的である。
琥珀とは、蚊や昆虫などが木の樹脂に覆われ化石化したもの。場所問わず世界のどの地域でも発見されている。
従来の輪島塗などの漆器は、基盤が木の「木地」だ。
その木地に漆を塗ったり、布着せなどを行う。長年かけてつくる漆器だが、木が割れたり、中が腐ったりすることが多いとのことだ。
だが、漆だけでつくられた作品であれば、「長年」どころか、万年レベルの耐久性となる。
最近、“漆”業界のほとんどの漆の9割以上が安価な中国産。日本産の漆と比較すると、中国産の漆の費用は半分以下。
業界問わず、可能な限り、原材料費を抑ることは今や“当たり前”のこと。だが、モノによっては、その“質”は落ちることもある。
輪島塗含め、いまや多くの漆器の漆は、中国産。安価だが、耐久性が良いとは言い難いそうだ。
質が微妙な漆器は、キズも付きやすい。そのような話しは、輪島塗 関係者から聞いたことがある。
「山崖松花堂」の漆器は、漆のみの器。しかも、最高品質の日本産の漆にこだわる。
製作に長年かかることから、もはや“アート”の領域。
“日本の漆のみで作られているため、湿気、漆の弱点である「乾燥」した地域など、気候が異なるどこの世界で利活用しようと、半永久的に長持ちするそうだ。どのような気候にも順応可能。
とにかく、残っていくもの、いわゆる「美術品」をつくりたい。その熱い気持ちをもった2人という印象だった。
“半永久的”なアートを追求
山崖さん兄弟は“アーティスト”という印象だ。時間をかけて、とにかく最高のものを作り、その“漆”作品を後世まで残したい。
芸術家である。
従来の漆器は、“経年劣化”がおき、長く置けば価値がなくなる。日本の伝統工芸で最も手間がかかるのにも関わらず、“美術品”として後世に残らない。
そこに悔しさと「違うのでは?!」「こんな手間暇かけて作っているのに残らない…」という疑問、そこに「辛さ」を肌で感じ、丈夫なもの、1000年、2000年、1万年の時を経ても、“残るもの”をつくりたいという背景から、「芯漆(しんしつ)」づくりが始まった。
輪島塗などこれまでの漆器とは異なる。ほぼ100%日本産の漆でつくる“アート”の新ブランドが「芯漆」だ。
漆は遥か縄文時代から、人々の生活で使われている。石器などからは必ず“漆”が使われていたそうだ。石器と木をくっつけるために、“漆”が使われていた。
木は腐って発見されるが、漆だけは残っている。また、武具でも多く使われていた。塩や米などと同等に漆は大切に扱われていた。
日本の土壌は酸性なので、化石が発見されにくく、溶けてしまう。漆を塗った部分は、塗った形のみが残る。
漆は、耐アルカリ性、耐酸性だ。鉄を溶かす酸ですら寄せ付けない。これをアルカリや酸の液に入れても、全く変化しない。漆は有機物の中でもっとも分子構造が安定している。他を寄せ付けない構造になっているそうだ。
戦争の戦艦、砲丸などにも漆が塗られていた。そうすることで船が錆び付かないからだ。
漆は“他”を寄せ付けない。しかし、弱いのは、木や布の部分。それらパーツが「劣化」を呼ぶ。
伸縮で木は割れてくる。そういう弱点を漆でつくることで、日本の伝統工芸「漆」を後世に残したい。
美術品になるものを選んでつくっている。日常ではあまり使わない「美術品」をつくる。
とにかく、「美術品」を目指す。
輪島塗はいつまで持つかとは厳密には言い難い。中に入っている木が弱点で、明日、明後日、10年、100年後には割れるかもしれない。
木が使われているため、修復しなければいけないわけだ。
修復しなくてももつものはゼロだ。
数の勝負では行いたくない。普通の漆器は半年で完成する。“芯漆”のお椀の製作には、(ものにもよるが)10年前後もかかる。安いものを作っても割が合わない。
「漆文化が廃れている中、漆が続く、新たな文化をつくりたい。持続可能な“漆”を残したい」「なるべく人がつくらないものをつくりたい」
漆自体は丈夫。樹脂の中でも最も質が高いと言われているほど。
“漆だけ”でつくれば、半永久的に残る。「労力かけて、努力してつくるのであれば、後に残るものをつくりたい」という背景から始めた。
漆器の根幹である「長年持つ」「残す」という本質を追及しているわけだ。
30年前に“漆のみ”のモノ作りを開始した。
「芯漆」は自由な形で作れる。「どうせつくるなら、世界に通用する、海外へ持って行っても、びくともしないような漆、美術品をつくりたい」と思ったわけだ。
本物、残っていくようなモノをつくりたい。
新たなブランド「芯漆」技法を打ち出していきたいと考えている。
労力かかるので、「漆のみ」を使った技法は他で行っていない。ぐい吞みだけで、7~8年かかるので、コストパフォーマンスは悪い。
この絵細かさは…まさに神業だ。
「乾漆(かんしつ)」という技法もあるそうだが、それは、麻布や和紙で形作ったものに、漆に木粉を練り合わせて、塗っている。純粋に“漆のみ”でつくられたわけではない。
価格も“そこそこ”、ぼくにとっては“高額”だが、1万年以上先まで持つことを考えると、価値は十分だ。後世まで永遠と残る。
もはや“アート”の領域である。
田舎旅で、この漆器を持っていたら格好良いだろうなぁ。
一度でもいいからこの100%漆の漆器で食事を食べてみたい。
「これは、輪島含め日本全国、他では作れない。たとえ、『人間国宝』に認定された人でもつくれないと思いますよ。私たちだけです」という自信を持った発言から感じられる熱い想い、今後も絶対に諦めずに取り組もうとしている姿が実に印象的だった。
ブログ村ランキング参加中!クリックをお願いします!
Please click below icon for a blog ranking

こちらクリックを!

|
お知らせ:『田舎バックパッカーハウス』をオープン!日本初の“住める駐車場” 能登半島にある小さな田舎町<石川県穴水町川尻>にシェアハウスとオフィス、コワーキングスペース、そして、住める駐車場・長期間滞在可能な車中泊スポット「バンライフ・ステーション」も! |

|
【お知らせ】牡蠣<かき>販売のサポート開始! 水揚げ直後の牡蠣<かき>があなたの手元に最速翌日届く!能登半島の“奥” 石川県穴水町岩車の牡蠣<かき>を購入!鮮度抜群なので、牡蠣ならではの臭みなし! |

























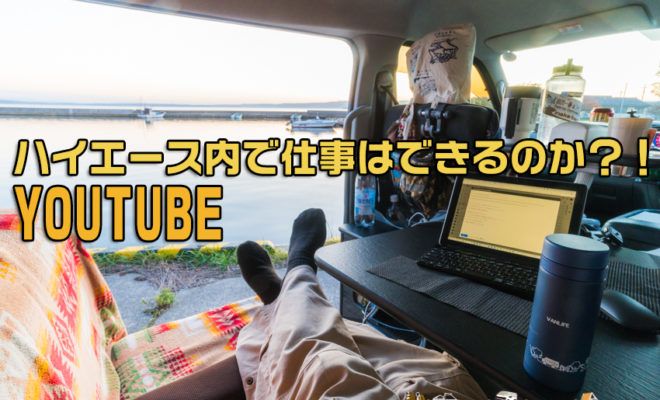





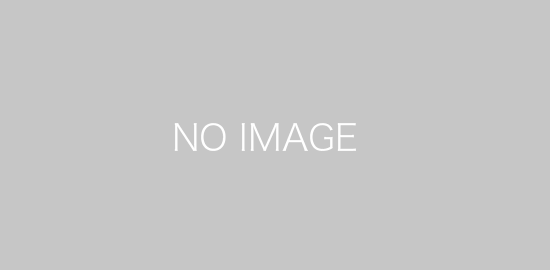























この記事へのコメントはありません。