つい先日の9月22日、石川県 地域振興課が名古屋で、移住/定住に関するセミナー「いしかわ UIターンセミナー & 相談会 〜 エリアごとに見る暮らしと働き方 〜」を開催した。
県庁からぼくに登壇の依頼があったのだが、セミナー開催日の9月22日は、移住先の岩車の「キリコ祭り」と、祭りを交えた「“ざっくばらん”な田舎ライフスタイル体験」でサプライズゲストが来てくれたので、セミナーに参加することはできなかった。(田舎体験お話しはこちら)
田舎/地方では、地元住民の祭り参加はマスト。まぁ、かなり極端な言い方ではあるが… “田舎の法”の1つのようなもの。
重要度の高い仕事や出来事などがあれば話しは別だろうが、よほどの理由がなければ、地元の大きな祭りの参加を避けることはできない。
だが、一方では、多くの現地住民の子どもたちは地元に戻らず、祭りに参加しないので、移住者もなんらか重要なことがあれば、“たまには”不参加でも「いいんじゃない?!」というのが、移住当初からのぼくの意見。
だが、やっぱりみんなで参加する祭りは楽しいからいいんだけどね。
まぁ、「祭り参加は絶対」に対する疑問は別として…
そんなこんなで、それら“イベント”ごとがあったため、移住セミナーでの講演は難しかった。
だが、講演では、役場がぼくに関する内容をお話しするとのことだったので、事前に講演用の資料作成をサポート。
約15分の枠で、内容を① プロフィール、② 穴水町に移住を決めた4つの理由、③ 一問一答、などにまとめたので、その内容をここで公開。
田舎に仕事はあるのだろうか?
田舎での「仕事」に関して追加して言えば、みんなが思っているとおり、田舎では「人口減少」「過疎化」が進み、空き家が増えている。
現実問題、最近、村を歩いていると、「誰が集会所の草刈りするの?」「宮の整備は?」「今ある畑はどうなるの?」など、細かいことについて、ついつい考えてしまう。
なぜならば、周囲を見ていると、ここ5年から10年の間で、多くの高齢者が亡くなることが予想できるからだ。
ここで言いたいことは、「若者が少ない」ということ。
そして、「若者が少ない」ということは、先端の技術、最近のテクノロジー関連について詳しい人が少ない。
ぼくらの親世代の50代後半や60代は、自身の息子や娘など周りにいる若手に、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターなどのソーシャルメディア、ホームページやブログ、スマホやパソコン、それらソフトの使い方、情報発信の仕方などについて聞きたいところだが、もはや周囲に親族となる若者がいないことが現実。
上の世代は、現代の事業において、それらツールを利活用することの重要性は報道などからもわかっているが、先端技術には中々ついていけない。
「それらがわかる人が周囲にいれば助かる」というわけである。これが「隙間ビジネス」となる。
田舎や都会問わず、もちろんのこと、中途半端な仕事は、どの世界へ行ってもNGなので、田舎でもしっかりと仕事することはマスト。
これはあくまでも一例だが、こういった細々した「隙間ビジネス」が田舎にはある。
だが、東京などの都会で、「できる人」だらけに埋もれていると、どうしても、「こんな単純なこと、誰でもできるだろう」と思いがち。
この「隙間ビジネス」の小さな仕事が積もれば山となるわけである。
だが、その「隙間ビジネス」を発見するには田舎現地に足を踏み入れ、「どんな“隙間”があるのか」を把握して、土台を築かなければ、わからない。
人口減少や高齢化が進んでいるからこそ、その「隙間ビジネス」がある、そして、それに加え、都会で埋もれるよりも、田舎/地方へ分散したほうが、『活躍の舞台=仕事が沢山ある』ということを言いたいわけだ。
移住・定住セミナーって今後も続けるの?!
あらゆるタイプの人がいるので、なんとも言えないが、もうこういった従来の“移住・定住セミナー”を開催するのは、「もういいんじゃない?!効果ってどうなのかなぁ?」と、最近思い始めている。
講演やセミナータイプなどの「ファーストステージ」は既に終わっていて、「田舎/地方の舞台を活用してどう生きる?」ってフェーズに入りつつある気がする。
今では、ソーシャルメディアなどを介して、移住、定住、田舎暮らし、地方活性化など、あらゆる情報が飛び交っている。
要するに、現地に関する情報や現地との触れ合いは、もはや「やる気があれば」すぐにできる。
ターゲット定めて、双方でコミュニケーションをダイレクトで気軽にとれる時でもある。
ソーシャルメディア上、都会に住んでいる田舎に興味がありそうな人を探しだし、ダイレクトでコミュニケーションをとる、そこに労力を費やしたほうが、新たな田舎移住・定住者増やすには効果的な気がする。
大衆よりも、個別アプローチだ。
今や知らない人たちが、直でメッセージをやり取りし、様々な意見を交換する時代だ。
そして、これからは、「田舎移住や暮らしの基盤整備」や「そこを活用してどうする?」ってステージ。
田舎現地で家を活用して、そこでどんなライフスタイルを築いていくのか…
今や個人が自由に動き周り、そこにいる人とダイレクトにメッセージを交わし、やり取りができる時代ってのに気づく必要がある。
そんでもって、新たな人がきたら、実際の現地での暮らしを見せる。
「本気で移住・定住を考えている人」のほとんどは、自分の足で、気になる田舎/地方に足を踏み入れて、“本格的”な現場調査をすることだろう。そういった人を日々探し、ダイレクトで個別にコンタクトする。
その人が「もやもや」しているところをサポートして、地方行政は、移住・定住につなげるべきではなかろうか。
ぼく自身が既に5年以上、田舎暮らしをしているから、こう思ってしまうだけなのだろうか…
話しはあちこちへと飛ぶが、言いたいことはわかるだろうか。
さて、これから、能登の田舎はどこへと向かっていくのだろうか。
ぼくも、そろそろ、もう一軒、コンディションの良い家を増やして、活動の幅を拡げていく予定だ。



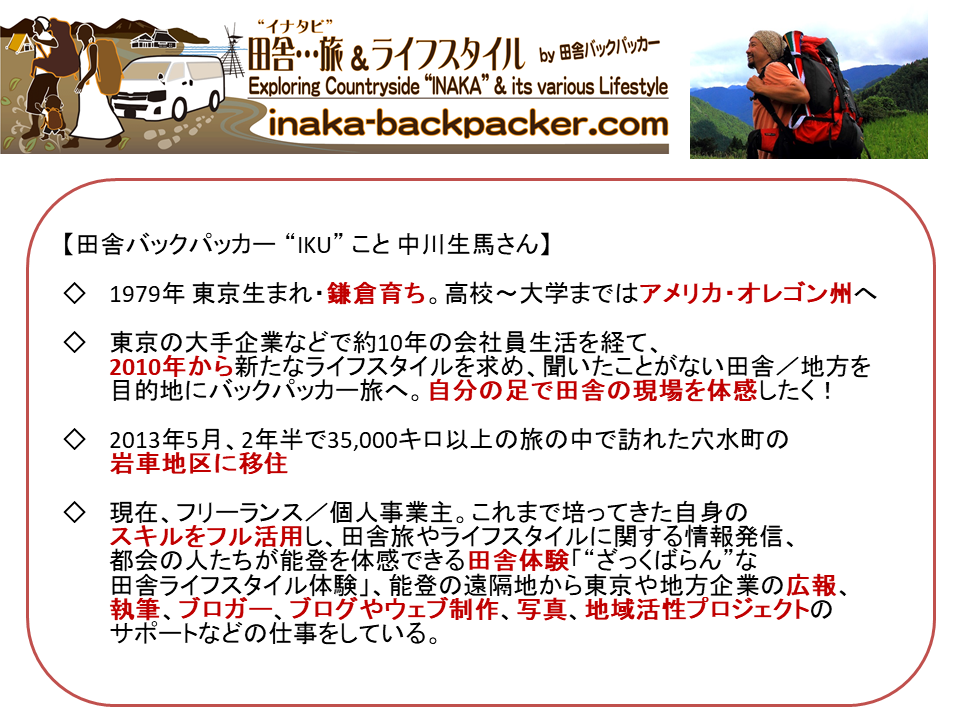

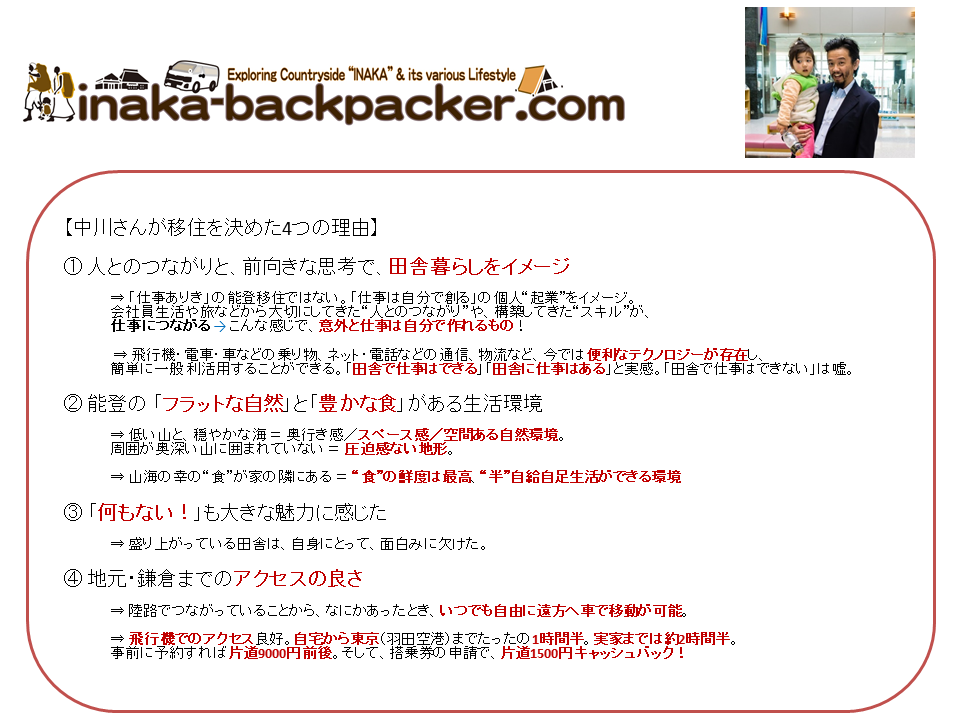
















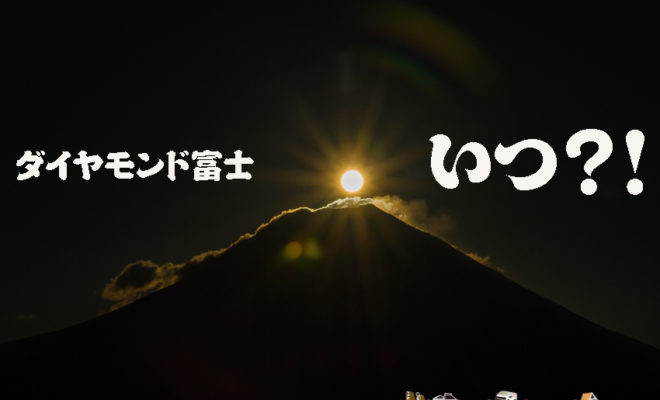

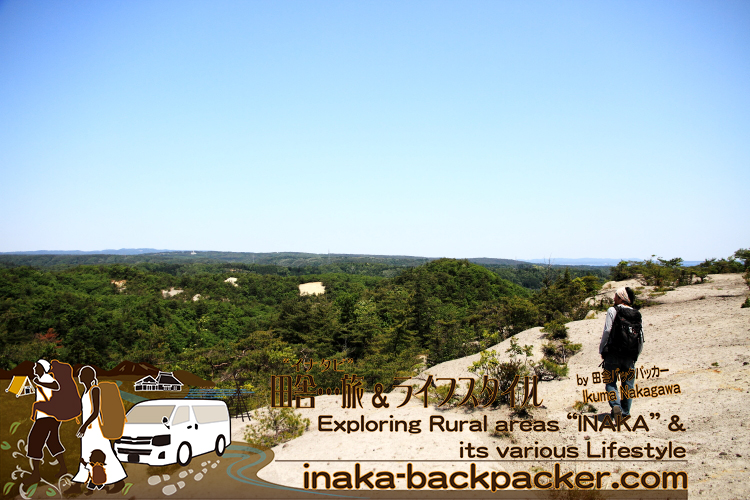





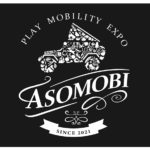
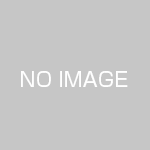

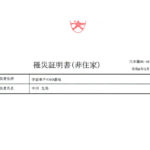

















この記事へのコメントはありません。